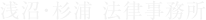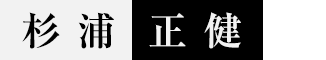永野修身海軍元帥の机
杉浦正健
私が事務所で愛用している机は、岳父浅沼澄次(事務所の創業者、私の妻利子の父)が、戦後の交詢社ビル(現在の新ビルが建替られる前のもの)に事務所を移して以来使用してきたもので、その没後、私が使わせていただいているものである。
私は、浅沼から、「この机は、永野修身氏(あの戦争開戦時の海軍軍令部総長、海軍大臣も歴任)が、大本営で愛用していたもので、戦後、相談を受けた仕事の報酬として譲受けたものだ」と聞かされている。私が、浅沼と机を並べて仕事をしたのは、その死没前のわずか五年間だけで、お互いに多忙を極めたこともあって、それ以上の事情について詳しく話を聞けないまま、岳父は旅立ってしまった。
記録(ウィキペディア)によると、永野氏は、大東亜戦争の開戦時は、海軍軍令部総長、大本営の本部員として、開戦の枢機にも加わっている。彼が軍令部総長を辞職し、大本営を離れたのは、昭和十八年六月なので、終戦の枢機には参与していない。戦後、戦犯として東京軍事裁判にかけられたが、逮捕されたのは終戦の翌年昭和二十一年の二月、そして、裁判途中の昭和二十二年一月二日、急性肺炎のため、巣鴨プリズンから聖路加国際病院に移送されたが、一月五日死去されている。従って、戦後、しばらくの間、「民間人」として、浅沼が相談を受けた可能性がある。終戦後、軍関係者は、世間の厳しい指弾にさらされ、軍人恩給もなくなり、加えて激しいインフレで、想像を絶する生活苦を背負われたことは、私もよく承知している。依頼した弁護士への報酬の支払にかえた由緒ある机を手放さざるをえない窮状も、理解できないわけではない。
浅沼が依頼を受けたのが、いつなのか、本人からなのか、その遺族からなのか、その内容はどのようなものだったのか、今となっては確かめる術はない。また、この机が、大本営から、永野家へ、そして浅沼へと渡っていることからすると、この机は、永野氏の私物であった可能性が高いが、「公用物」であったかもしれない。目の肥えた来客から、時折、机の由来をたずねられる度に、浅沼に詳しく話を聞いておかなかったことを悔やまざるをえない。
この机の、重厚さ、使い込まれた、堂々たる姿、風格をみると、私は、この机は、浅沼が言っていた通り、「永野さんが、大本営で愛用していた」ものであることを疑う余地はない、と感じざるをえない。
この机を、永野さんがいつ頃から愛用されたのかも定かではないが、おそらく、海軍兵学校長になられた(昭和三年)か、軍令部次長になられた(昭和五年)か、いずれにせよ海軍のなかの指導的立場になられたころであろう。永野氏は、海軍兵学校卒業(明治三十三年)後、まもなく、日露戦争に加わり、旅順攻囲戦や、日本海海戦で武勲を樹てた生粋の海軍軍人であり、その後、ハーバード大学にも学び、アメリカ大使館付武官を勤めるなど、国際情勢に精通し、大の親米派で、駐米大使館勤務時代には「軍人でなければ、(アメリカ)に住み続けたい」と話していたという。あの戦争の開戦にも消極的で、陸軍の独走をくい止められなかったことをいたく反省し、極東軍事裁判でも、一切弁明せず語らず、戦争を防止できなかった責任は自らにもある、とした態度を貫かれたという。
この机は、語ることをしない。しかし、この机は、長年、戦争に向っての大きなうねりのなかで、苦悩する永野さんの姿や、永野さんの周辺の人々の動きを目にしてきたはずである。
机よ、心あらば、何を語るのか、と想いながら、机に向う日々である。
赤髭弁護士浅沼澄次の足跡
杉浦正健
私の岳父(妻利子の父)、浅沼澄次弁護士(以下岳父と略称する。)は、昭和五十二年十月十日この世を去っているので、今年は、その没後四十年にあたることになる。光陰矢の如しである。
ホームページに岳父について書くために、岳父の没後編集出版されたその追悼録「偃蹇浅沼澄次」を久しぶりに読み返してみた。
私にとっては、岳父とは、その末娘利子と昭和三十八年に結婚する数年まえからの二十年ほどのこの世のご縁であったが、追悼録に寄せられた多くの方々(追悼録はA5版で六〇〇ページにもなる大部なもので、執筆者は一五〇人をこえる。)の岳父への想いを読み進むにつれ、忘却の彼方に沈んでいた、さまざまな想いが生き生きと蘇がえってきた。
「人の価値は、棺を蓋うて定まる」とはどなたの言われたことか知るところではないが、世に広くいわれていることであるけれども、岳父について、身内が口にするのは如何かと思うものの、正にその通りだ、と思わざるをえない。府立一中、一高、東大法学部卒という超エリートでありながら、官途に就かず、在野法曹一筋に清貧の弁護士道を貫き通し、弁護士として大きな業績も挙げたその一生は私など、遠く及ぶところではない。
まず第一にすばらしい多くの友人達に恵まれていることである。追悼録の執筆者を一目みるだけで、驚きを通り越してしまう。明治の世に生れ、大正のよき時代に一中、一高、東大と俊秀の集うところで教育をうけられたことは、岳父の天賦の能力の高さを示すものだが、それだけではない。とりわけ一高(一高に限らず、旧制高校すべてにいえることだと思うが)時代、全寮制で三年間、同世代の全国から集う俊秀達と「同じ釜の飯を食べて」切磋琢磨し、学友や恩師たちとの間で培われた絆の深さは、戦後、新しい学制のもとで、中・高等教育が「大衆化」されたなかで育ったわれわれからすると理解を超えたものである。岳父のまわりに集う雲のように多くの友人・先輩・後輩たちの交友を目のあたりにして、羨望を禁じえなかった。追悼録の井本台吉先生、浜本一夫先生ら友人たちの追悼文をごらんいただければ、皆さんの友情の一端は、ご理解いただけるのではないか、と思う。
島に対する岳父の想い入れの深さは、尋常ではない。岳父が「島」と口にするとき、その生れ故郷である八丈島だけでなく幼少年期を過した南大東島、三宅島をはじめとする伊豆七島、遠く離れた小笠原諸島、時には硫黄島など太平洋に浮かぶすべての島々を含むものだった。私が岳父と共に仕事をした五年間でも、事務所は「島」の人々が数多くひんぱんに出入し、あたかも「島」の東京出張所の観を呈していた。「島」の人々から依頼されたことは、何であれ断ることはなかったし、「事件」の処理は文字通り手弁当で報酬は置いていけば受け取ったと思うが、そのような状景は私は見たことはない。
岳父の「島」に対する献身と貢献は八丈島郷友会長奥山善雄氏と八丈島末吉郷友会長沖山冶信氏の弔辞に詳しく述べられているし、後述の八丈島老母殺害事件の「被害者」である。小崎米蔵氏の寄稿文「一族の恩人」でも語られている。
平成十二年一月、南大東島の開拓一〇〇周年を記念して、南大東村の主催で盛大な記念行事が行われた。
岳父は南大東島発展の功労者として表彰されることとなり、遺族を代表して妻利子が記念式典に招待され、参加することとなった。私は、その配偶者として、妻に同行し、生れてはじめて南大東島の土を踏んだ。南大東村作成の記念式次第には岳父の功労として「南北大東の「土地問題」に当たり両大東農民の主張の正当性の立証に時間と出費を自弁して開拓農民の権利の擁護に努められた」とあった。式典会場の一角には岳父のコーナーが設けられ、故人の遺影とともに、その使用した万年筆や眼鏡などが展示されていた。
一月二十三日に行われた式典では妻が開拓事業主である玉置半右衛門(初代)の像の除幕者の一人となり、その後行われた祝賀会では私が、感謝のごあいさつをさせて頂いた。
南大東島は東西約六キロ、南北六.五キロ、周囲二一キロ、環状の高い丘陵が島を太平洋から切離し、中央部はくぼんで盆地となっており、一見すると火山島を思わせる。しかし、実際は火山島ではなく、広大な珊瑚礁が長い年月(おそらく、数千年、数万年だろう)をかけて、隆起した環礁である。島をとりまく環状の丘陵は高さが三〇~四〇メートルあり、太平洋の荒波で削られ、岸辺は一〇~二〇メートルの高い絶壁となって、人を寄せつけず、玉置半右衛門が開拓事業を始めるまでは無人島だった。ただ、島は、台風の進路上にあることから、水は豊富で中央の盆地には植物が繁茂し、土地も肥沃で、玉置は、開墾すれば、サトウキビの栽培には適していることに着目したようである。玉置の着眼は正しかった。
玉置半右衛門は、事業着手に先立って二度に亘って慎重な事前調査を行い、明治三十三年八丈島々民を主に二十三名の第一陣を島に送り込んでいる。入植は難儀を極めたが、資材等の補給に万全を期したことも与って開拓は進んでいった。岳父は、明治三十五年六月三日八丈島末吉村に、父浅沼幸一、母多だの三男として出生し、三才のとき(明治三十八年ころ)父母らと共に南大東島に移住したので、玉置半右衛門の事業開拓後、五年が経過しており、開拓もかなり進んでいた。(記録によると明治三十八年には、人口は四二二名、戸数は九二戸に達していた。)明治四一年には玉置が玉置小学校を開設(開設時の児童生徒は七十八名であった)したので、岳父は、それに入学したことになる。
岳父の玉置小学校時代については、追悼録中の菊地富士雄氏の「心の故郷」に、岳父が特待生であったこと、なかでも、その中で一人だけ玉置家の「書生」の栄誉を受けた第一号であったことなど詳しく書かれている。
岳父は玉置小学校を卒業後、親戚を頼って鹿児島、東京を転々とし、四ツ谷の小学校で一年、再度の六年生を修了した後、府立一中、一高、東大と進学するのだが、もの心ついたころから少年期を過した南大東島の凄絶な自然環境と、玉置家での「特待生」という修業・苦役の影響が、岳父の人間を形成するうえではかり知れない貴重なものであったことは疑う余地がない。岳父が「島」を愛し、その事務所が「島」の出張所の観を呈していたのも、その為であるといえるであろう。
岳父の成し遂げ、残した弁護士としての業績も他に比類がない。
終戦ころまでの事跡としては戦争中のゾルゲ事件と八丈島老婆殺害事件が挙げられる。ゾルゲ事件については、岳父は当初は官選弁護人、まもなくゾルゲの親任により私選弁護人として弁護に当った。事件については、著書も多数なされており(映画にもなった)追悼録でも井本台吉先生や平松勇先生が触れておられ、本ホームページに岳父のゾルゲについての感想を掲載させていただいたので、詳しく触れる必要はないだろう。歴史に残る事跡といってよい。八丈島老婆殺害事件も、追悼録で相弁護人の井本台吉先生と、被害者遺族の小崎米蔵氏が詳しく触れているところである。事件の詳細については岩波新書で出版されており、えん罪事件として引用されることも多い、これも歴史に残る足跡である。
戦後のものとしては、昭和電工疑獄事件がある。当時、昭和電工の社長だった日野原節三氏と岳父が、一高、東大で親友だったことから(岳父は昭和電工の法律顧問を仰せ付かっていた。)贈賄側で訴追された日野原氏の弁護人の一人として弁護に立ち、控訴審までの実刑判決を最高裁で覆し、執行猶予をかちとったのだった。その詳細は、追悼録の田中康道先生の文に詳しい。最高裁の段階で執行猶予が付せられた(情状論だけで)のは空前であり、おそらく絶後なのではないだろうか。
昭和電工事件ほど有名ではないが、私が弁護士登録してまもなく受任したものに博報堂事件がある。当時博報堂のオーナーで会長だった瀬木博政氏(博報堂の創業者で発行株式の大半を所有ないし支配していた)から、岳父との一中、一高、東大の友人だったことで依頼を受けたものだった。当時の社長が術策を弄して、発行株式の大半を支配下に置き、瀬木一族を経営から排除しようとしていた。岳父は有力弁護士事務所の協力の許に、社長を特別背任で告訴し、訴追・有罪に追込んで瀬木一族に経営権を回復することに成功したのだった。弁護士登録したばかりの私にとってもたいへん勉強になった事件だった。
しかし、私が岳父の足跡が凄いと思うのは、述べたような大事件を解決に導いたことだけではない。岳父が一中、一高、東大という戦前の超エリート教育を受けながら、官途にも就かず、世俗的な栄躍栄華の人生も求めず、在野の弁護士の道一筋に、清貧の人生を貫いたことにある、と思うのである。岳父は、その一生で、おそらく何千件という事件(その殆どが民事事件だった)に取組み、数え切れない人との相談に乗り、その問題の解決に心を砕いた。そのことは追悼録に寄せられた多くの方々の文章で触れられている。弁護士としての岳父の信条は、事務所の第一号のイソ弁だった神田洋司先生はじめ多くの友人の弁護士の追悼文に詳しく書かれている。岳父が残した遺産は、事務所の外は中野の小さな(四〇坪くらいの土地)家屋敷の外は目ぼしいものはなかった。まさしく「赤髭」弁護士といってよい生涯を全うしたといってよいと思う。
岳父の人となりについては追悼録に寄せられた方々の文章をお目通しいただければ、よりよく理解していただけると思う。とりわけ、岳父の晩年の事務所を支えて下さった神田洋司、湯坐一衛、尾崎宏氏諸先生、事務員の原田アヤ子さん、白石英彦君、小山長一郎君の追悼文は、岳父のひととなりを余すところなく伝えてくれている。事務スタッフの皆は、「どなられっぱなしの毎日」を送りながら、夫々長年尽くしてくれた。原田さんに至っては岳父没後も、五〇年をこえる才月を事務所に捧げ、今日も尚、週二日は出勤し、文字通り事務所の大御所である。
岳父の人となりを一言でいえば、尾崎宏弁護士を紹介して下さった鈴木竹雄先生が尾崎君に言われたという「一高生がそのまま社会人になったようなところがある。」が核心を突いているように私も思う。実に天真爛漫で憎めない、人から愛され、また尊敬された人だった。追悼録を出版したことで、私ははじめて知ったことだが、岳父が一高在学中に駒場寮寮歌(第三十五回記念祭)を作詞していたことである。作曲者である竹中雪さんの追悼文に詳しいが、岳父の一高生としての真骨頂をみる思いである。
岳父とのご縁ができたなかで、今日に至るまで、残念に思っていることは、岳父が戦前、戦中のわが国について、どのように想い、考えていたのか、詳しく聞けなかったことである。
岳父とじっくりと話す時間が持てるようになったのは、もちろん、私が弁護士となってからの五年である。その五年間のうち最後の一年は岳父が病気勝であったし、その余の四年間も、岳父が一弁の会長を勤めた後も、東京都公害審査会委員(委員長代行)、法制審議会委員、固有財産中央審議会委員、弁護士協同組合理事長など公務で多忙を極めたこと、私自身も湯坐弁護士などの力を借りながら、岳父の顧問先等依頼者だけでなく自分自身の依頼者も急増したため、岳父とは事件の打合せをする時間もままならない状況だった。それに加えて、岳父は健康そのもので誰もが長生きされるものと信じて疑わなかったことも挙げねばならないだろう。
私は岳父から、明治から大正・昭和とあの戦争への道をわが国が歩んだことについて、その歩んだ道を礼讃することも反対に政治を批判することも、一切聞いたことはない。岳父は、私がアジアの留学生や技術研修生受入れ事業に没頭していることを熟知したうえで、末娘との結婚を承諾したわけだし、戦時中、だれも引受手のなかったゾルゲのスパイ事件を、官選弁護人とはいえ引受けたこと、といい、あの東京大空襲の際には、高円寺からの火の手が中野に迫り、あと二百メートルぐらいで中野の住居も危い状況だったのが、風向きが変って危地を脱した経験もあり、廃墟と化した東京で、弁護士の仕事を続けていた、ことからしても、「あの戦争」についての想いが、なにもなかったとは思われない。
岳父が、あと五年十年長生きし、仕事の第一線を離れて悠々自適の人生を過せるようにならないままに旅立ってしまったことが、かえすがえすも残念に思う昨今である。
事務所の名を現在の浅沼・杉浦法律事務所としたのは、私が、政界を引退し、弁護士に復帰してからである。「浅沼」の名を残したのは、弁護士としての岳父のレガシーを残したいという想いがあるのはもとよりのことだが、現在事務所を支えていただいている多くの顧問会社のなかに、今尚、浅沼時代から引続いてご協力いただいている会社がいくつもあるという事情もある。誠にありがたいことである。
現在のわが事務所は、私が八十路を過ぎたことで(幸い元気で健康には恵まれているのだが)参画してくれている若い弁護士たちと共に、親しい多くの優れた弁護士の皆さんの協力を頂いて業務を何とか恙なく処理できているのであるが、それも誠にありがたいことである。
今のところ、杉浦の家系からも浅沼からも事務所の後を継ぐ有資格者は現れていない。従って今の事務所の名前が将来も残るかどうか定かではない。しかし、私は当然のことながら死を免れることはできないが、この事務所をそっくり誰かに継がさなければ死にきれない、とも思ってはいない。梶とる舟師は変るとも、岳父や私が、やりたいことを貫いてきた精神が、何らかの形で受継いでもらえればいい、と思っている。
以上
一法曹の見た人間リヒアルト・ゾルゲ
浅沼澄次
一介の弁護士たる私が共産主義者としての大立物であるゾルゲ氏のことどもを語ることは甚だ不似合であり、おこがましい様な気もする。只私は彼の為めに微力な弁護を引き受けたものとして巣鴨拘置所の窓を通して幾度か話した中から薄れ行く記憶を辿りつつとり止めもない筆を運ぶ次第である。
私が最初ゾルゲに会ったのは昭和十七年二月の末頃であったかと思ふ。当時既に巣鴨の拘置所に拘留中であった彼は日射を受けた弐階の小さな室で検事立会の許で私に面会をした。何分国際的事件の中心人物であるので私の心は可成り緊張した。最初受けた感じは實に如才のない何等悪びれもせず愛嬌たっぷりと云ふ態度であった。此の男があれ程の諜報活動をやったのかなと全く意外の感に打たれた。餘程煙草を欲しかったらしく手まねで笑ひながら煙草を一本飲み度いと云ったので検事のお許しを得て確か一本か二本飲ませたことであった。彼の表情は一切解脱したものの如くさへ見えた。今にして思へばその時既に自己の運命に対する腹が決って居たのではなかったらうか。彼の声はすき通っては居なかったが物軟かく割合にゆっくりした語調であった。その応対振りは厳格な拘置所の不自由さを他所に快活で人を外さぬものがあった。一回として不愉快な顔を見せなかったのは何としても大勢の纏め役として平素の心構への表現でもあったらうか。彼はロシア人たる母と独乙人技師との間の子供であり兄弟姉妹八名の中の確か四番目の生れである。彼の先天的性格は両者の血の結合から胚胎したかも知れず独乙人の持つあの一徹な所は一見掴むことが出来ない。彼の頬は稍々肉が落ちて居ったが面長で締った口と軟かいまなざしには強い意思と怜悧さを湛えて居った。当時四十七才の彼にはまだ若さが消えず立居振舞も至極元気に見えた。総体的に云って拘置所内の生活が彼の身体に格別の障害を興へなかったことは確かである。私の独乙語は至極拙いものであったがそれでも短時間の面接の間に不充分ながら用務の打合せも出来た。時には突拍子もないことを云ひ出すことがあった。それが日本語であることもあった。ゆかた(浴衣)せっけん、その他まだあったと思ふが思ひ出せない。日本語にかけては甚だ他の一連の外人被告に比して話が下手な彼がゆかたと云ふ言葉を知っていたのには一寸驚いた。丁度熱い時であったので洋服のみではやり切れず湯上り後にゆかたでも着たいと云う意味であらう。早速その手筈を調へて届けたこともあった。窮屈な房の中でゆかたに煙草一服ならどれ程本人が喜ぶことだらうと独り考へ乍ら拘置所を出たことも一回や二回ではなかった。正式の妻を持たない彼が家庭的にも拘束されず検擧前その活動の為め實に奔放にして自在な生活環境に処して華やかであったのに引き換へ此の拘置所の世界は一切を失わざるを得ない。その前身を思ふが故に弁護人としても一般人並に簡單に済まして居られぬ故かゆかたと煙草の結び付きはほぐれ得ぬものがあったのである。拘置所の面会では職務上の打合せ以外は彼が外人たるが故を以ても許されなかった。然し彼は一寸した間隙を見て独乙語で世界の、特に独乙とソ聯との戦線の動きを訊ねることがあった。その質問は實に冷静であり、何れが進まうが退かうが悲喜の情を表に出さなかった。
終りには独乙が段々後退することが分っても只黙って居る丈であった。自由の身なら談を発したであらうが許されざることを私に聞くことが既にいけないことであり私の答へに更に答へることが自分にも弁護人にも悪いことになると思って居た様子は之またはっきりして居った。それだから独乙語の問答は一回切りの簡單なものであった。外界の情勢を知りたがるのは人情である。殊に自己の総力を舉げて共産主義祖国ソ聯の為めに、日本と独乙の動きを調べて居った彼が何とかして刻々の世界情勢を知り度いのは人一倍切なる願望であったのであらう。然し彼の望みを叶へてやることが出来なかったのは法の前に於ける弁護人の立場として是非もないことであった。彼は対談中よく手をこすり頭を左右にふることがしばしばあった。もっと何か話して呉れと云ふ表情である。私の胸はその都度深い哀愁に包まれた。話して別れる時は何時も強い握手をしてアウフ・ウィーダーゼーンを交した。大きな手の平で私の手首を握りしめ時には両手の平で私の右の手指を握り乍らやさしいまなざしとにこやかな笑顔で立ち別れたことも何度かあった。私として更に辛かったのは何時死刑になるのかと手真似をし乍ら聞かれることであった。而かもその態度たるや何等の屈託もなく例の温顔に笑をたたへつつ平然無関心の如き所は一層私の心を撹き乱した。それで居て他の被告等のことを名指して如何なったか、元気か、会ったら本人によく傳えて呉れなどと何時も心を配って居た。眞の大親分でなければ到底達し得ない境地であらう。彼が共産主義者として徹底して居った眞骨頂は端的に右の言動の裡に見られたのである。彼は非常に頭脳の良い男であった様に思ふ。その拘置所内の讀書力もいささかも衰へず歴史物にかけては全く片端から讀破すると云ふ風であった。私は彼から色々本の註文を受けた。戰争は漸く苛烈となって空襲も頻々たる中を私は遥々神戸迄行って彼の好きな歴史の書籍を買ひ集めて興へてやったことも数回あった。そのなかには彼が非常に喜んで呉れたものもあったがなかには之はつまらないとか既に讀んで了ったとか云ふものがあった。東京の丸善等には斯る書籍は最早見当らなかったので関西の古本屋を漁ったのである。神戸には外人が多勢居った故か洋書は相当多かったと思ふ。拘置所内の渇を癒すものは唯一つ書籍のみ。知識内容の豊富さを貴ぶものに取っては殊に然りである。時には西洋の有名な畫家の畫集も差入れした。
拘置所の係官がいやな顔もせず出来るだけの便宜を計って呉れたことは幸であった。
〇原文のまま